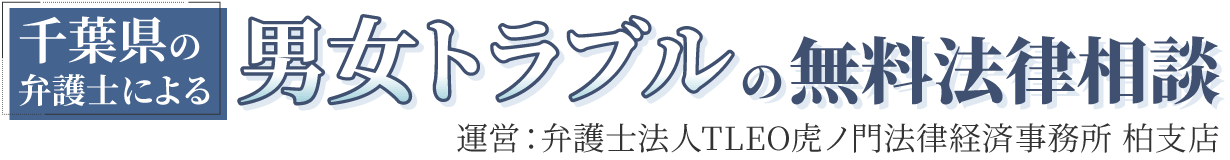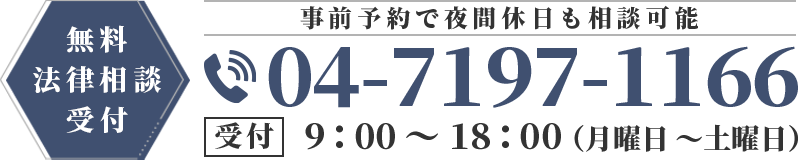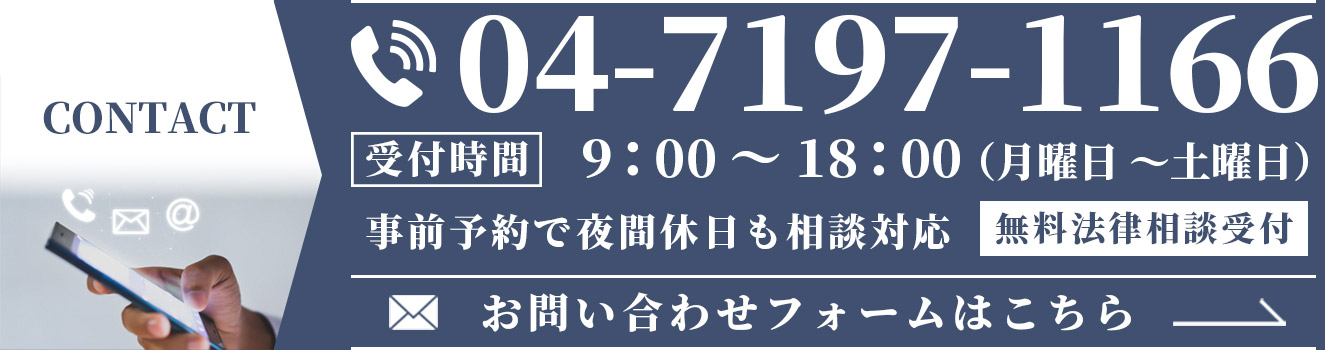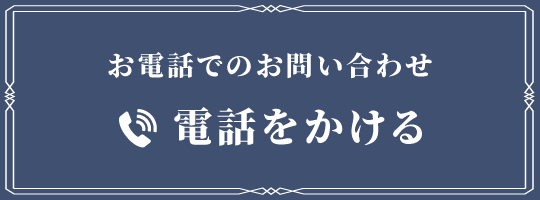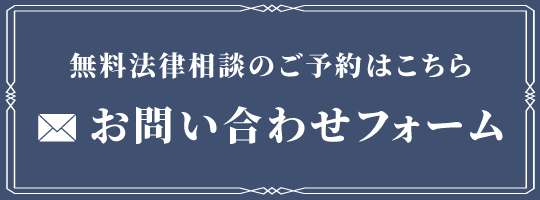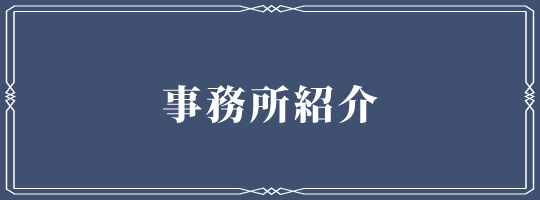このページの目次
別居時に生活費の確保に悩まれている方へ
「夫婦関係がうまくいかず、離婚を視野に入れて別居を検討しているが、別居後の生活費をどうすればよいかわからない…」というお悩みを抱えている方は少なくありません。
別居を決断したとしても、毎日の生活費の不安が残ってしまっては安心した生活を始めることができません。
そこで今回は、別居中に生活費(婚姻費用)を確保していくための具体的な方法や注意点、さらに法的手続きを通じて生活費を確保するためのサポート制度や支援内容をわかりやすくご紹介します。
別居中の生活費(婚姻費用)とは?
夫婦は結婚している間、お互いに協力して生活を支え合う義務があります。この義務は、別居中であっても継続します。そのため、収入の高い方は、収入の少ない方に対して一定の生活費(婚姻費用)を負担する義務があります。婚姻費用には、具体的に以下のような費用が含まれます。
- 衣食住に関する費用(食費、住宅費、光熱費)
- 子どもの教育費、養育費
- 医療費、保険料
- その他の日常生活に必要な経費
収入のない専業主婦(主夫)やパート勤務で収入に不安がある方でも、婚姻費用を相手に請求することで、ご自身の生活費を確保することが可能です。
婚姻費用の相場の目安と計算方法
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入状況や子どもの人数・年齢などをもとに算定されます。裁判所は「婚姻費用算定表」を公開しており、これに基づいて金額を決めることが一般的です。婚姻費用算定表(参考例)
| 相手(義務者)の年収 | 請求者の年収 | 子ども1人(0~14歳)の場合の婚姻費用(月額) |
| 400万円 | 0~100万円 | 約6~8万円 |
| 600万円 | 0~100万円 | 約8~10万円 |
| 800万円 | 0~100万円 | 約10~12万円 |
実際の支払い額については、細かい家庭状況ごとの調整がありますので、弁護士など専門家に相談して具体的にご確認されることをおすすめします。
別居後、生活費を確保するための具体的な方法
① まずは相手方との直接的な話し合いを行う
最も迅速で簡易な方法は、相手方と直接コミュニケーションを取り、「婚姻費用の金額」「支払いの方法とタイミング」を合意の上で決定することです。この合意は必ず書面に残し、「婚姻費用分担合意書」などの形で作成することをおすすめします。
② 書面で合意できない場合は調停を申し立てる
直接の話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることができます。裁判所調停委員の仲介によって双方の事情や収入状況を踏まえ、公平な婚姻費用を取り決める手続きを行います。調停手続きの申し立て費用は1件あたり1,200円(収入印紙代)で、比較的負担も少ない点がメリットです。
③ 調停でまとまらない場合は審判手続きへ
調停でも合意に至らない場合、裁判官が一定の金額を決定する「審判」手続きへと移行します。審判で決定された婚姻費用は法的強制力を持ちますので、相手方が支払わない場合には強制執行(給与差押え等)を行うことも可能です。
婚姻費用請求手続きの流れと期間の目安
一般的な手続きの所要期間は以下の通りです。
- 話し合いによる合意:数日~数か月程度
- 調停を申し立てた場合:3か月~1年程度
- 審判へ移行した場合:6か月~2年程度
できるだけ早い段階で話し合い、合意に至る方が早期に生活費を確保できます。自信がない場合や話し合いが難しい場合は、早めに弁護士へご相談されるのがよいでしょう。
生活費確保のための法的支援~弁護士に依頼するメリット
婚姻費用の交渉は収入状況や資産状況を考慮するため、けっして簡単でない場合があります。こうした状況では、弁護士の法的支援を受けることで多くのメリットを得ることができます。
- 適切な婚姻費用額の算出と早期の請求を行える
- 直接、相手方とのやり取りを避けられ、精神的負担を軽減できる
- 調停申立てや審判手続きにおいて、有利に手続きを進められる
- 婚姻費用支払いが滞った場合の強制執行もスムーズに行える
まとめ:別居中の生活費の確保を一人で悩まず弁護士に相談を
生活費の問題は別居後の生活を左右する重大な問題です。お金に関する交渉を自分一人で進めるのは、精神的にも大きな負荷がかかるものです。
当事務所では、婚姻費用に関する豊富な知識を持つ弁護士が、個別のケースに合わせて親身に対応いたします。初回相談は1時間無料で提供しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。